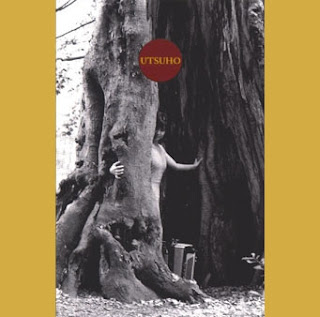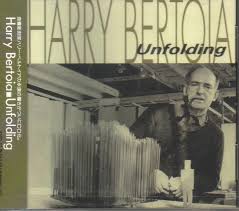当時はライブをやってなかったんですよ。それまでとは違うやり方をしたくて自分に新しい名前をつけて『うつほ』を作りました。本格的にライブを始めたのは2003年からで、主に高円寺のペンギンハウスや千駄ヶ谷のループラインでやってました。残念ながら両方とも今はありませんけれど。
ー2000年頃からà qui avec Gabrielと名乗るようになったのですね。 それまでの活動とは違うことを始めようと思ったのは何かきっかけがあったのですか?
時間が経つうちに自分のやり方で表現したくなったんだと思います。2001年の夏ごろからこの名前になりました。
ーなるほど。アコーディオンを始めた頃はソロでの演奏にはさほど関心がなかったのでしょうか?
そうですね。バンドがやりたかったので。
ーどんなバンドをやりたかったのですか?また高校生の頃の受付嬢バンド以降、何かバンドをやっていましたか?
地元のバンドが見せてくれた音の交感のようなことを自分もやってみたかったんだと思います。受付嬢以降はTumba Creole トゥンバ クレオールというアフリカやブラジル、カリブの音楽をやる十数人編成のバンドに参加しました。私以外は全員錚々たるスタジオミュージシャンで90年代の中頃六本木のピットインなどで演奏してました。pneuma hectopascal(プネウマヘクトパスカル)を作ったのはそのあとでドラムの夏秋文尚さんとコントラバスの河崎純さんとのトリオでした。
ーカリブ音楽ですか。今のアキさんからは想像できないですね。Tumba Creole にはどのような流れから参加することになったのでしょうか? pneuma hectopascalはどのような音楽性のバンドだったのですか?
学生時代に民族音楽サークルで知り合った方がTumba Creoleのリーダーだったのでそのご縁です。プネウマでは小さなモチーフを用意してそれを発展させるようなことをやっていました。曲のイメージやモチーフを即興していくような感じです。
ーああ、やはり民族音楽サークルからの繋がりだったのですね。Pneuma Hectopascalはロックバンドだったということですが、 即興でロックをやっていたということでしょうか?
ええ、ただ完全即興ではありませんし、所謂ロックというジャンルには当てはまらないかもしれません。当時は多少とんがってたので「長髪でギター弾いてるだけでロックだと思うなよ!」とか思ってましたから。(笑)
ーなるほど、アコーディオン、コントラバス、ドラムという編成はロックバンドとしては特異だなと思っていましたが、 アキさんならではのロックの表現形態がPneuma Hectopascalだったということですね。ちなみに Pneuma Hectopascal で 演奏をする上でインスピレーションを受けた音楽はありますか?
インスピレーションをもらったのは音楽以外のものからで、例えば「子供奴隷の反乱」という曲はヘンリー・ダーガーの絵画から、「ウズベク・キーパー」という曲はニキータ・ミハルコフの映画「ウルガ」からといった感じです。「ウルガ」の舞台はモンゴルですがイメージしているうちにウズベキスタンに跳んじゃいました(笑) ちなみに「ウズベキスタン」という言葉の語源である「O’zbek」には「自身が主君」という意味があるそうです。実際何を意味しているのかわかりませんが自分の主君が自分自身だっていうのは「Rock !」ってことなんじゃないでしょうか。(笑)
ーそれがアキさんのロックの定義ということですね。ところで、10代の頃にご覧になったロックバンドの ライブでは音がまるで動いているように感じ、絵画や映画から音楽のインスピレーションを得ている とのことですが、アキさんはいわゆる共感覚をお持ちなのではないですか?
共感覚という定義に当てはまるのかわかりませんけど、他の何かからインスピレーションを得るっていうのはそんなに珍しいことじゃないと思います。
ーなるほど、ライブで音が動いているような感じがしたという話は初めて聞いたもので、気になっていました。音源をお聞きしてないだけに、プネウマの音楽に対する想像力が高まるのですが、あえていうならば、どのグループの音に似ていますか?
「音は動いたりしないし、見えたりしませんよ」って教育されちゃうと思うので忘れ去られてしまう感覚なのかもしれませんね。プネウマは何に似ていたのか思いつきません。
ーなるほど。プネウマとしては何年から何年ぐらいまで活動していたのでしょうか? また、音源をリリースするというような話は出なかったでしょうか?
2005年から2007年ぐらいまで活動しましたけど音源をリリースするには至りませんでした。私が未熟過ぎて録音したいって気持ちになれなかったんですよね。楽曲を即興でやりたかったんですがうまくいきませんでした。今思えば、あの時歌が歌えていたらもっと違ったアプローチができたかもしれませんね。バンドとしての活動はしなくなってしまいましたが、夏秋さんも河崎さんも素晴らしいミュージシャンでプネウマは面白い体験でした。お二人にはすごく感謝しています。
ー即興で楽曲のようなものを作るというコンセプトがとてもユニークに感じます。ライブが見れなかったのが改めて残念です。 ところで、アキさんはいつから歌を歌い始めたのですか?また、そうしようと思ったきっかけは何ですか?
プネウマのあとのソロは「一人プネウマ」だと思ってやっているので、バンドでやりたかったことを少しは感じてもらえるかもしれません。 歌はもともと歌いたかったんですが、アコーディオンで歌うっていうのはなんか違うなって。蛇腹を動かす呼吸をしながら歌うための呼吸をするっていうのは制限がかかる感じでしっくりこなくて。そんな中、いろいろな人と一緒に演奏するようになって、楽器から手を放して歌える場面が増えて行きました。中でも仲良くなったフランスのミュージシャンMichel Henritziミシェル・アンリツィは日本の演歌が大好きで「今回は一緒に藤圭子をやろう」なんて言うんですよ。それで演歌のカバーを始めました。
ーミッシェルさんの勧めでアキさんは演歌を歌うようになったのですね。 ミッシェルさんとはどのようなきっかけで出会い、コラボレーションを始めるようになった のでしょうか?
ミシェルとは10年ほど前に高円寺のペンギンハウスで出会って一緒に演奏するようになりました。
彼はただ「演歌をやろう」って言っただけなので歌うように勧められたわけじゃないんですよ。でも歌うことにして(笑)一緒に演歌やムード歌謡のカバーアルバム「こよなく」を作りました。それから、私にとって初めての欧州ツアーをNo Neck Blues BandのMicoさんとデュオで回るという面白い形でオーガナイズしてくれて、その後も欧州で演奏する機会をたくさん作ってくれました。ミシェルは素晴らしいミュージシャンであるとともに非常階段のJunkoさんや浦邉雅祥、秋山徹次、三上寛や友川カズキなど数多くの日本のミュージシャンをヨーロッパに紹介してきた人です。彼が日本のアンダーグラウンドシーンについて書いた本も昨年フランスで出版されました。
ーミシェルさんはアキさんの音楽活動の幅を広げた存在だったのですね。 Micoさんとの欧州ツアーはどのようなものだったのでしょうか?実はMicoさんについてあまり知らないので、まず彼女のことについて教えて頂けますか?
 |
子供の頃に懐メロ(昔の流行歌)として聞いていた曲を歌ってみたいなと思って選びました。「小雨の丘」だけは大人になってから聞いた曲ですが、以前バイトしていた「中級ユーラシア料理店元祖日の丸軒」っていう摩訶不思議なお店で戦前の昭和歌謡ばかりが流れていてどハマりしました。ガブリエル(アコーディオン)を入手して最初に路上で演奏したのもそういった昭和歌謡でした。
ー「こよなく」は2016年にリリースされていますが、アキさんにとってはある意味原点回帰 のような作品だったのでしょうか?また、録音はフランスで行われていますね。 非常に生々しく、まるで目の前で演奏しているかのような録音ですが、 この時のレコーディングはどんな様子だったのでしょうか?
原点回帰ではなくて新しいことに挑戦してる感じでしたね。歌い始めたばかりでしたし。 録音はLe Singe BlancというハードコアバンドのドラマーだったKevin Le Quellecがやってくれました。メッスにあるケビン所有のなんか棲んでるでしょ?ってカンジの地下スタジオで。生々しく聞こえるとしたら、それはケビンの録音のセンスとあの地下スタジオのエネルギーのせいじゃないでしょうか。あそこは演奏した人たちの魂が刻み込まれているような場所でしたから。歌、アコーディオン、爆音ギターというバランスのとりにくい組み合わせだったのでアイディアを出しながら3人で進めていきました。
ええ、Electric Wizardも場の響きやエネルギーを感じて録音場所を選んでいると思います。 最初はカバー曲だけ録音するつもりだったんですけど、やってるうちに全体の収録時間が足りないかも?! って話になって(笑) それで慌てて自分の詩を持ち出して来ました。他の曲をカバーしても良かったんでしょうけど、当時はまだ歌える曲が少なかったので。
ーなるほど、そういう訳だったのですね。さて、「こよなく」の発売と同じ時期の2015年に 工藤冬里さんとのスプリットEP、「情趣演歌」をリリースされてますね。この作品はどのような 経緯で作られたのでしょうか?
ミシェルから友達のセドリックがやっているAn’archiveというレーベルで演歌カバーのスプリット盤をシリーズ化していくようだからやってみない?って。で、やりたい!ってことでピアノの弾き語りで「女のブルース」「好きになった人」「港町ブルース」をカバーしました。工藤さんは「柳ヶ瀬ブルース」「東京ブルース」「骨まで愛して」をカラオケで熱唱しています。
ーこのスプリット盤に収録されている工藤冬里さんとは以前からつながりがあったのでしょうか?
スプリットの組み合わせはセドリックが決めたものですが、工藤さんとはそれ以前に一度共演したことがありました。スプリットの話が進んでいる最中にもMaher Shalal Hash BazとChé-SHIZUと一緒に「マイナー・ミュージック・ジャパン・ツアー」(笑)って名前のツアーでアメリカに行きました。友人のミュージシャンChe Chenチェ・チェンが勇敢にもこの風変わりなツアーを企画してくれました。
ーチェ・チェンさんはどのような音楽を演奏している方なのですか?また、マイナーミュージック・ジャパン・ツアーにまつわる エピソードを教えて下さい。
チェ・チェンは75 Dollar Bill というニューヨークの実験的なバンドのギタリストです。民族音楽にもかなり詳しいので研究者みたいな側面もあると思います。加えてすごく良いヤツです。ツアーではシェシズやマヘルの一員として演奏する傍ら私たちを引率してくれました。 カリフォルニア芸術大学の野外音楽堂を皮切りに、L.A.のギャラリーChin’s Push、テキサスの砂漠の町マーファのクロウリー・シアター、デトロイトの現代美術館、ブルックリンのISSUE Project Roomとめぐりました。どの場所も印象深くて、そこで生活している人たちも含めてまるで不思議な物語のようでした。出発前に周りの人から、強烈な個性の皆さんと一緒のツアーだけど大丈夫?と心配されましたが、各所で入れ替わるマヘルの人たちも含めて物語の登場人物は皆役者ぞろいで楽しめました。ちゃっかりこのツアーに潜り込ませてもらい、こんなに面白い体験ができたのもチェ・チェンのおかげです。
ー話を聞いているだけでワクワクするようなツアーですね。 話は「情趣演歌」に戻りますが、演歌のカバー集というのは当時目新しかったと 思うのですが、反響はどのようなものだったでしょうか?
演歌のカバー云々ではなく私が歌い始めたことに対して賛否両論ありましたね。アコーディオンじゃなくてピアノで歌い出したので「アベック・ガブリエルじゃないのか?」とか。「君はアコーディオニストなんだから!」とか言われました。違和感があったんでしょうね。逆にいいね!って言ってくれる人も結構いて、日頃は厳しいセンパイに褒めてもらったり、曲をリクエストしてくれる人がいたり、オススメの音源や映像を次々に送ってくれる人もいて、うれしかったですね。ともあれ、批判も含めて何か引っかかるものがあったなら良かったと思ってます。
ーそのような批判があったのですね。アコーディオンを使わず、歌を歌い始めた時に、ご自身ではどのように感じていましたか?
より自由に表現できるような、可能性が広がる感じがありましたね。自分なりのピアノの弾き方を探ったり、弾かないことでアコーディオンの面白さに改めて気付いたり、曲をカバーすること自体の楽しさもあってノリノリでやってました。(笑)
ー曲はどのような基準で選んだのでしょうか?また、他に候補となった曲はありましたか?
ゴールデン街の裏窓というお店で、オーナーの福岡さんが藤圭子が好きなミシェルのために「女のブルース」をかけてくれたんですけど、ああこれだと思いました。あとはなるべく有名なものをと思って都はるみの「好きになった人」と森進一の「港町ブルース」を選びました。何をカバーしてるのかわかった方が楽しいかなと思ったので。他には川内康範の歌詞が好きなので「君こそわが命」「逢わずに愛して」「誰よりも君を愛す」などが候補でした。ただ演歌っていうよりムード歌謡っぽい気がしたので、最終的にはより演歌っぽいと思える3曲に決めました。堀さんはこれらの曲をご存知ですか?
ーなるほど、私は 「女のブルース」 だけは何となく知っていましたが、それ以外の曲は知りませんでした。 さて、時代は前後するのですが、2012年に魔術の庭、さらに河端一さんとコラボレーション作品をリリース していますね。彼らと一緒に演奏するようになった経緯を教えてください。
世代が若くなるほど演歌を耳にする機会は少なくなるのかもしれませんね。 魔術の庭は、光束夜のベーシストだったsachikoさんを通じてリーダーの福岡林嗣さんと知り合ったのがきっかけです。河端さんとはスズキジュンゾさんを通じて知り合って、河端さんが彦根のスミス記念堂で続けているライブシリーズでデュオすることになって以来ですね。
ー魔術の庭とのジョイント作品「第五作品集Ⅱ」を聴かせて頂きました。 聴く前のイメージではサイケデリック・ロックの激しいサウンドとアコーディオンをどう合わせるのかと 思っていましたが、魔術の庭のスローでソフトな演奏とアキさんのアコーディオンが見事にはまっていますね。 共演前に作品の方向性についてどのような話し合いをしていたのでしょうか?
ありがとうございます。 事前には、2部作のうちのアコースティック・バージョンだということと、曲のヒントとして福岡さんの故郷北海道が舞台のマンガを貸してもらったぐらいで、作品の方向性について話したことはなかったと思います。魔術の庭の美しい楽曲が方向性を示してくれていましたから、あまり話す必要はなかったんだと思います。でもミックスの段階では結構話し合いましたよ。色々な発見があって面白かったです。
ーなるほど、この作品は二部作としてリリースされ「Ⅱ」はアコースティックな方だったわけですね。 ミックスの段階の話し合いではどのような発見がありましたか?
感覚をコトバにして伝える必要があったので、自分の中では当たり前すぎてあまりコトバにしてこなかった感覚を意識させられましたね。
ーなるほど。福岡さんのミックスに関する考え方はどのようなものだったのですか?
そうですね。福岡さんは空間を音で埋め尽くしたいと思っているようでした。爆音のライブ会場みたいに音が部屋を覆い尽くしてるカンジ。私は音が届いていない余白のようなものが欲しいと感じていました。抜け感のようなものです。その方が壁が消えて広がりを感じることができるから。逆に大きな世界に行けるような。なんとなく伝わりますか?
ーええ。アキさんはいわゆる”間”のようなものを重視していたわけですね。私がCDを聴いた印象では、 この作品のミックスはアキさんの考え方に近い仕上がりになっているように感じるのですが、ミックスに関する話し合いはどのような形に 落ち着いたのでしょうか?
堀さんは耳が良いですね。そうなってると思います。ミックスは福岡さん自身がやっていたので、「もっとこうしてみましょうか」とか「もうちょっと湿気がある感じ?」などと感じたことをコトバにしながら実際にやってみて体感で決めていきました。
ー音全体にふんわりとした柔らかさがあり、雪景色のような情景が浮かんでくるように感じます。 どの曲も秀逸ですが、アキさんがバック・ヴォーカルも務めている一曲目の「潮騒」が特に印象的ですね。 この曲を録音した時のエピソードを教えてもらえますか?
ステキなイメージでなんだかうれしくなりますね。 「潮騒」は荻窪のスタジオで利光暁子さんに一緒にコーラスできるように譜割(リズムに歌詞をどのようにのせるか)を教えてもらいつつ録音した記憶があります。この曲を最初に録音したんじゃなかったかな?そのぐらいの記憶で、あとはあんまりよく覚えてないです。
ーなるほど。このアルバムリリース時にライブやツアーは行いましたか? もし行っていたら、その時の反響を教えてください。
ライブもツアーもやらなかったんですよ。何でやらなかったのか覚えてませんが(笑) 実際ライブで爆音のバンドと一緒にやるのは音量差がありすぎてなかなか難しいんです。アコーディオンにコンタクトマイクを付けたりプリアンプで音を持ち上げたりとやりようはあるんですけど。私はスタンドマイクに楽器を近づけたり離したりすることでダイナミクスを作っているので、コンタクトマイクはなるべく使いたくないんですよね。プリアンプも音はデカくできるけど出したい音じゃなくなっちゃうし。だから私が難しいって言ったのかもしれません。それか、この後ベースの影山さんが地元に戻ることになってバンドを抜けたので、そのことによるものだったかもしれません。
ーそうでしたか。アキさんのサイトにもライブの記録がなかったので、確認してみたいと思いました。 それでは、河端一さんとのコラボ作品「Golden tree」についての質問になりますが、 この作品を作るようになった経緯について教えてください。
一緒にライブをやった後に音源も作りましょうってことになったんだと思います。
ーその「Golden Tree」ですが、長尺の曲が3曲でドローンの要素も入ったスケールの大きな 作品に仕上がっていますね。制作にとりかかる前に何かお二人の中でコンセプトやイメージ のようなものはありましたか?
コンセプトやイメージといったものはありませんでした。録音した音を聞いた時に世界樹みたいなものが思い浮かんだので「Golden Tree」というタイトルをつけました。スケールの大きさを感じるとしたらそれは河端さんゆえですね。一緒に演奏するといつも宇宙に連れて行かれるような感じがするんですよね。
ー完全に即興で作り上げた作品なわけですね。具体的には音のどういった部分から世界樹を連想されたのですか?
感覚的なことなので具体的に説明するのは難しいかもしれません。後付けでそれらしいことを言えるのかもしれませんが(笑) 論理的なものではないってことだと思います。
ーなるほど。それでは、世界樹とはアキさんにとってどういう存在ですか?何か特別な思い入れがあったのでしょうか?
音を聞いて思い浮かんだイメージってだけで特別な思い入れがあるわけじゃないんです。世界が一本の樹でできているなんて壮大なイメージですよね。そんなふうに想像力を掻き立ててくれるもの、この世界をどう眺めても良いんだっていう自由な感覚に気づかせてくれるものっていう感じでしょうか。
ーなるほど。正直なところ、世界樹というものに馴染みがなかったのでどこで知ったのかなと思いました。 曲目も「神籬」「輪環」「暮露」とここでもあまり耳にしない言葉が出てきますね。こういったタイトルに したのはどのような経緯でしょうか?
世界樹っていうのは色々な国の神話に出てくるんですよ。だからどのタイトルもイメージです。特に伝えたいメッセージがあるわけじゃないし、こうとってくれっていうのもないし、だからもっと遊び心でつけてます。何をどうイメージするかは捉える人の自由だと思うので。アルバム名は世界樹ではなく「Golden tree」です。ブルース・リーの言葉通り、Don't think! Feel ! です。(笑)
ーそういうことなのですね。見たことがないような言葉を使われているので、何かそこに特別な意味や エピソードがあるのかと思いました。「Golden Tree」リリース翌年に、再び河端さんとのデュオ作「天の剣」を リリースされていますね。録音日は「Golden Tree」と同じようですが、最初から2部作としてリリースする予定 だったのでしょうか?
タイトルや曲名は小さな詩のようなものだと思ってもらえたら良いのかもしれません。英語のタイトルと併せてアルバムを聴きながらイメージが広がると良いなと思ってつけてます。 結果として2枚のアルバムになったってことで、そうなるとは思ってなかったですね。即興でやっているものに関しては計画のしようがないんですよ。
ーなるほど。河端さんとはこのアルバム2作以外に、ライブでも何度か共演されていますね。 アキさんにとって河端さんは音楽家としてどのような存在ですか?
一緒に演奏すると宇宙に連れて行かれるような感じがするんですよ。気がつくと宇宙にいるみたいな。(笑) ソロにしてもデュオにしてもAcid Mothers Templeにしてもとにかくスケールが大きいなと思います。威厳のある大河のように音が流れてくるよなぁといつも思いますね。
ー河端さんとは関西、四国など様々な場所をツアーされていますが、その中で最も印象的なエピソードを教えて下さい。
ー河端さんとは関西、四国など様々な場所をツアーされていますが、その中で最も印象的なエピソードを教えて下さい。
ひとつのエピソードを選ぶのは難しいですけど、とにかくよく呑んでいっぱい話をしたなと思います。それぞれの場やそこにいる人たちを感じながら楽しくツアーさせてもらいました。河端さんという人物の面白さとそのフィールドに集まってくる人たちの面白さで何かこう豊かなんですよね。そういうものも含めて音になっているというか。うまく説明できませんが、河端さんのライブに行ったりブログを読んだりしたら私の感じていることが少しは伝わるかもしれません。
ー2019年に新曲「はらり」をYoutubeにアップされましたね。今までのアキさんの楽曲とは趣きが異なるように感じましたが、ご自身ではいかがですか?また、今後の活動のプランについて教えてください。
「はらり」は2013年に録音した曲なんですよ。自分としては違和感ないですが、違って聞こえるんだろうなっていうのもなんとなくわかります。声を重ねて録っているせいもあるかもしれませんね。 今後については全くのノープランです。(笑)à qui avec Gabrielとしての活動はひとまず終わりにして、また新たに何かしたいなと思っているところです。